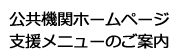実効性の高いドキュメント整備が成功の鍵
[ 2005年4月27日 ]
 執筆担当
執筆担当
大久保 翌
(おおくぼ あきら)
ウェブサイトのアクセシビリティ確保を成功に導くためには、組織個別にドキュメント(文書)を整備することが重要です。2004年6月に JIS X 8341-3(以後、JIS規格) が制定されましたが、民間企業や地方公共団体では、独自にどのようなドキュメントを用意するべきなのでしょうか。
実際に、ルール共有やノウハウフォロー、業務改善・効率化などに役立たなければ意味がありません。昨今、作成事例が増えてきた「ガイドライン」を題材に考えてみましょう。
取組みの手始めにガイドラインを整備する企業や自治体が増加
アクセシビリティの取組みに関係するドキュメントとして最もポピュラーなのは、アクセシビリティガイドラインと呼ばれているものでしょう。意欲的に取り組んでいる民間企業や地方公共団体では、独自に作成し公開する事例も増えてきました。目標設定に始まり、外部調達(内部制作)、組織内の体制整備、研修(教育)と様々な取組みが求められる中で、早い段階で組織としてのルールを整備することは非常に重要です。その意味で、ガイドライン整備の事例が増えているのは理に適ったことだと言えます。
総務省が開催中の研究会が地方公共団体を対象に2005年2月から3月に実施した 調査結果 では、配慮のための作成指針を独自に作成したとしている自治体が、回答自治体のうち13.5%。作成している割合は自治体の規模が大きくなればなるほど増加し、都道府県では8割が作成したと回答しています。
有効にガイドラインが機能していないという現実も
しかし、実際に運用されている現場に話を聞きに行ってみると、作成したガイドラインが有効に機能している例は、残念な事に少ないようなのです。
- 現場の社員(職員)の人が読んでくれず制作に活かされていない
- 外部発注や検収に事実上活かせていない
- 詳細な文書がサイトで公開されているものの、利用者にとっては難しく意味が分からない
本当のところを伺っていくと、こういったケースがかなり多いことが分かります。
ガイドラインの制作・公開は、組織の内部にとっても、利用者に向けたメッセージとしても、成果として分かりやすい取組みと言えるかもしれません。しかし、 「立派そうなガイドライン」を作成したり公開したりするだけでは、実際の業務改善、ウェブサイトやウェブシステムのアクセシビリティ改善には繋がらないというのが現実のようです。
なぜこのような事になってしまうのでしょうか。
ドキュメント整備の成否で、取組みの成否も左右される
一般にアクセシビリティガイドラインとよばれているものを見てみると、3つの役割を期待されているようです。
- 外部調達や、内部制作のアクセシビリティ仕様を示すものとして
- 制作に携わる社員(職員)をフォローするマニュアル・リファレンスとして
- 利用者をはじめとして内外に対して取組みの目標や成果を示すものとして
これらは、対象者あるいは役割が明らかに異なっていますが、これらを「ガイドライン」という言葉でひとつのドキュメントに漠然と仕立ててしまうと、結果的にどの役割も充分に果たせない半端なものになってしまいます。上記の残念な事例でもこの事は大きな要因のひとつだと考えられます。
目指すべきは、 誰のためのどのような役割を持ったドキュメントが必要とされているかを充分に整理した上で制作し、実際にそのドキュメントを機能させる ことです。このような実効性の高いドキュメント整備が出来るのと出来ないのとでは、アクセシビリティの取組みの実現レベル、品質の継続性が、結果的に著しく異なると言っても過言ではありません。
それでは、実効性の高いドキュメントとは具体的にどのようなものでしょうか。
アクセシビリティ仕様を適格に示す「対応基準書」
前節の3つの役割のうちのひとつ「アクセシビリティ仕様を示すもの」を例に考えてみましょう。
外部の制作会社に調達をかける場合でも、内部で作成する場合でも、アクセシビリティに配慮したコンテンツとなるようにルールが必要です。一般にはこれも「ガイドライン」と呼ばれている事が多いのですが、幅広く捉えられてしまうことの弊害も多いので、そのドキュメントに期待される役割を踏まえ「対応基準書」と呼ぶことにして話を進めます。
あくまでJISをベースに、独自に決めなければいけない部分を詰める
国内のガイドラインとしては2004年6月にJIS規格が出来ました。JIS規格制定以前は、日本語のコンテンツを前提に日本語で書かれた規格が存在しなかったこともあって、それぞれの団体が独自に試行錯誤してガイドラインを整備していました。しかし、その状況はJIS規格制定によって変わったと考えるべきでしょう。
企業や自治体でもJIS規格と同じようなものを独自に編み出そうするケースが見受けられます。私は、基本的にこれはデメリットの方が大きいと感じています。JIS規格にも考えが至っていない点があるかもしれません。またJIS規格の文書の体裁が読みにくいとか、表現が難しいとか、買わないと入手できないというようなことがハードルになっているという話も聞き、それぞれもっともな事だと思います。しかし、それらを勘案しても、国内の専門家の方々が相当の時間をかけて練り上げたJIS規格を活かさない手はありません。また、そもそも2重のルールがあちこちに出来るという状況は避けるべきです。
ただし、JIS規格をそのまま使えば良いかというと、それでは足りないために「対応基準書」が必要になります。JIS規格は、多様なウェブコンテンツや技術の発展を念頭に制作されているので、あえて表現を具体的にしないように注意して作成されています。しかし、ある特定のウェブサイト、ウェブシステムを調達(制作)する場合には、表現は逆に具体的で無ければ意味を為しません。いざ制作しようという時には、「~することが望ましい」では、要件にならないわけです。
組織で個別に用意する「対応基準書」では、JIS規格が整理して示したアクセシビリティの要件をその組織ではどう捉えて具体的にどう対応するのか、場合によってはしないのかという方針を決め、実際の制作の基準となり得るレベルのルールとして定めることが重要になります。
「発注元」「制作会社」、双方にとってドキュメント化のメリットがある
このようにきちんとドキュメントを用意することは、様々なメリットがあります。
例えば「対応基準書」の場合では、発注元の担当者と制作会社との間で、制作対象のコンテンツではJISの要件にどのように対応するのかを明らかにしておくことで、双方の合意に基づいた目標を設定することが可能になります。ある自治体で、JIS規格に対応するようにと指示して調達したウェブサイトを、事後に専門家に診断してもらったところ多くの問題点を指摘されるということがあったらしいのですが、そのような場合も双方の合意による目標が設定されていれば、責任の有無、あるいは責任の所在が明確になるわけです。
また、次回の修正やリニューアルの際にどのような見直しをすべきかについての拠り所にもなるはずです。指摘された問題点だけを闇雲につぶそうということでなく、体系的に整備した仕様のどこをどう改善するかという検討が可能になり、前回の成果を踏まえた効果的な対応が出来ることになります。
終わりに
現在までのところ、企業や自治体のアクセシビリティ確保の取組みでは、多くの場合、暫定的なとりあえずの対応を行ったり、あるいはサイトのリニューアルを行ったりというケースが多いと思います。アクセシビリティは出来る対応からはじめる事が肝心ですので、このこと自体に問題はありません。
しかし、年月の経過や担当者の異動などに左右されること無く、アクセシビリティの確保されたコンテンツを提供していくためには、その組織にとって実効性の高いドキュメントを整備していくことが欠かせません。既にガイドラインやチェックリスト、ポリシーなどを作成されている場合は、それが実際に機能しているかどうか見直してみて下さい。また、これから取り組まれる場合には、有効に機能するドキュメントの整備を検討しましょう。
実効性の高いドキュメント整備の重要性と意義については、今後このA.A.O.の中で、「ウェブアクセシビリティ確保標準手順」として情報を公開していく予定です。ご注目ください。
関連コラム